一般皮膚科 DERMATOLOGY


一般皮膚科 DERMATOLOGY
みずほ台サンクリニックの一般皮膚科は、かゆみやブツブツ、赤く腫れている部位がある、いぼがある、やけどをしてしまった、ウオノメやタコが出来て痛いなど皮膚に関するお悩みについて、保険診療にて幅広く診療しております。
皮膚は昔から「全身を映す鏡」といわれています。大半は、皮膚そのものが原因の皮膚疾患のケースが多いですが、栄養不足や何らかの全身疾患による症状として、皮膚に何かしらの炎症、かゆみ、肌荒れ などが現れることもあります。単なる湿疹やかぶれだと思って来院された患者様が、何らかの内臓疾患を罹患していたということも少なくありません。
そのため、あらゆる可能性を排除することなく診察を行い、必要な場合は血液検査や画像検査なども組み合わせて総合的に診断をいたします。
主な皮膚疾患 DISEASE
| 湿疹・皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 かぶれ 蕁麻疹 口内炎 |
|---|
| 皮膚感染症 | いぼ 水虫 爪水虫 帯状疱疹 にきび とびひ |
|---|
| 外傷 | やけど 擦り傷 虫刺され |
|---|
| 皮膚腫瘍 | できもの ほくろ |
|---|
| その他 | 円形脱毛症 タコ |
|---|
※粉瘤の切除術、巻き爪の根治術、保険でのレーザー治療は行っておりません。
みずほ台サンクリニックの
いぼ治療
MEDICAL TREATMENT
いぼの種類と原因
CASE 01
老人性いぼ
30歳代から徐々にできはじめる、紫外線の影響や加齢、体質などが原因とされている皮膚の良性腫瘍です。
- 脂漏性角化症
- 顔、首、手などによく見られます。色は褐色から黒色まで様々で、やや盛り上がりがあり、表面がざらざらしているのが特徴です。
- アクロコルドン、スキンタッグ
- 首にできることが多いですが、首以外にもまぶたやわきの下、胸など皮膚が薄くて弱い部分に見られます。皮膚の良性腫瘍の一種で、特に心配な病気ではありませんが、衣類でこすれたり、ねじれたりして炎症を生じることがあります。
CASE 02
ウイルス性いぼ
ヒトパピローマウイルスの感染によって発症する腫瘤です。ウイルスは皮膚の小さな傷から入り込んで、皮膚の角化細胞に感染し発症するため、触るとどんどん増える傾向があります。
- 尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)
- 手指、足の裏にできるウイルス性のできものです。ウオノメやタコと間違われやすいため、自分で触ってしまうと触れた手指などに移ってしまいます。
足底部などで体重がかかる場所にできたものは、いぼが深く食い込んでしまい難治性となることも多いです。 - 青年性扁平疣贅(せいねんせいへんぺいゆうぜい)
- 思春期以降に主に顔面や手、背中などにできやすく、皮膚面からの盛り上がり方が少なく、滑らかな表面をしています。
液体窒素治療について
当院では、液体窒素によるいぼ治療を行っております。
いぼの治療法として最も一般的な治療法が、液体窒素による冷凍凝固術で、主にウイルス性いぼの中心となる治療方法です。
液体窒素でいぼを焼くことで、ウイルスを殺し、また凍傷を引き起こして皮膚表面の異常組織を壊死させるというものです。
具体的には、マイナス196℃の液体窒素でいぼを凍結させます。いぼを焼いたあとは感染した皮膚ごと壊死して剥がれていきます。
当院でもいぼの治療の第一選択肢とさせていただいており、週1回の頻度で、2ヶ月程度繰り返し治療を行います。

- 01痛みを感じる方が多い
-
液体窒素の冷凍凝固術は、小児など痛みに弱い患者様は治療の継続が難しくなる場合もあります。
施術頻度は1~2週間おきに数回~10回以上と、継続して治療を受けないと十分に効果を発揮しません。そのため、定期的に治療をしないと完治することは難しいでしょう。
痛いと感じるのは、いぼを液体窒素で治療してから1~2日程度ですが、痛みに耐えられないという方には削るのみの方法や漢方薬など、他の治療法で対応いたします。また、液体窒素での治療後に血豆や水ぶくれが生じることがあります。もし水ぶくれが潰れてしまった時は消毒やガーゼで保護するなど化膿しないよう対処が必要です。
- 02悪化するケースも考えられる
-
液体窒素の冷凍凝固術を行ったあと、焼いたいぼの周りに小さないぼができてしまうことがあります。
これは、ウイルス性のいぼを液体窒素で焼いた時に細胞が潰れて、いぼの原因であるウイルスを周りの部位にまき散らしてしてしまうことが原因です。まれなケースではあるものの、患者様によっては冷凍凝固術を行ったあとに、小さかったいぼが広がり悪化する場合もあります。
- 03長期化してしまう場合もある
-
液体窒素による治療は、1回で治ることがほとんどなく、治療期間が長期化する場合が多いです。
個人差はありますが、1~2週間ごとに治療を行い、早ければ2、3回で治る方もいます。しかし、冷凍凝固術により皮膚が固く厚くなってしまい、かえっていぼが治りづらくなることもあります。そのため、治療に長期間かかる方もいます。
このように、液体窒素を用いた治療期間は個人差が非常に大きく、事前に予測することは難しいです。
- 04治療後に跡が残ることがある
-
冷凍凝固術を行うと、液体窒素療法を行った方の9割の方に炎症後色素沈着(シミ)ができます。
色素沈着は、液体窒素治療後大体1ヶ月後ぐらいにでてきて、消えるまでに半年~1年ぐらいかかります。また、いぼよりも一回り大きい痕が残ることもあります。そのため、当院ではシミが気になる場合や、顔や首など目立つ部位に小さないぼがたくさんできてしまったような場合は、冷凍凝固術ではなく炭酸ガスレーザー治療などを推奨することが多いです。この場合は、他院へのご紹介になります。
液体窒素によるいぼ治療の流れ
いぼの種類や状態を見極めたうえで、液体窒素による冷凍凝固術を第一選択として治療をスタートします。

液体窒素による治療は、1~2週間に一度のペースで通院していただき、状況を見ながら2ヶ月程度は治療を継続していきます。

2ヶ月間の冷凍凝固術を行っても改善しない場合は、削る処置や漢方薬などを追加することがあります。
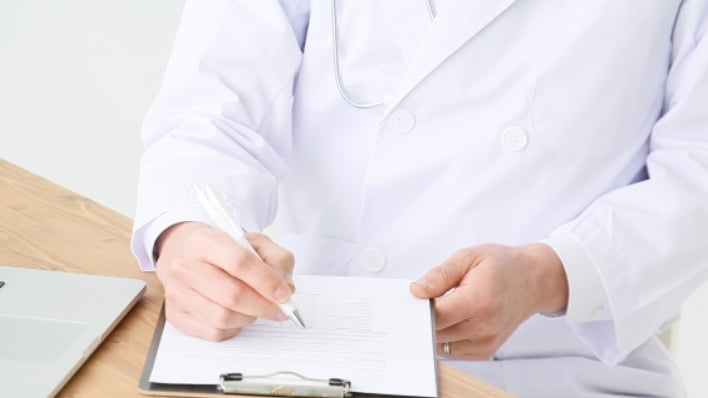
担当医師のご紹介 SPECIALIST DOCTOR
- お名前
- 板東 大晃(ばんどう ともあき)
- 略歴
-
- 総合病院で全科研修
- 都内クリニックで男性医療に従事
- 男性専門クリニック開設
- 取得資格
-
- テストステロン補充療法認定医
- 日本抗加齢医学会認定専門医
- 日本医師会認定産業医
- 高濃度ビタミンC点滴療法認定医
- キレーション認定医
- 厚労省認定オンライン診療研修修了
- メッセージ
- さまざまな症状に対して、つらい思いをされている方も多いと思います。
皮膚トラブルでお悩みの方はぜひご相談ください。
- 一般皮膚科
のお問い合わせ・ご予約はこちら -
Web予約
24時間受付中!


